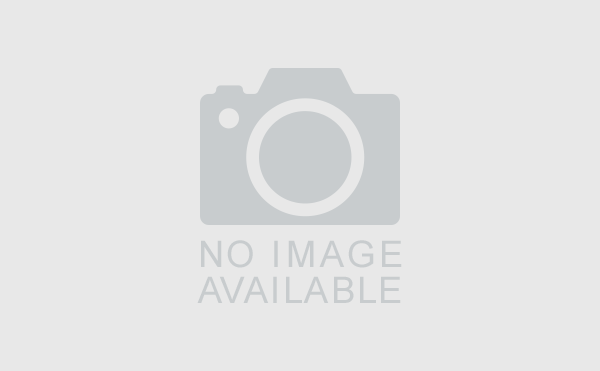内部留保とは?誰でもわかる仕組みと意味を解説
「内部留保」という言葉をニュースや決算発表などで耳にしたことはありませんか?
「会社がお金をため込んでいる」と思われがちですが、実際には少し誤解があります。この記事では、内部留保の基本的な意味から、企業経営における考え方までをわかりやすく解説します。さらに資金繰りとの関係も触れ、実務で活用できる視点をご紹介します。
内部留保とは?基本の意味と仕組み
内部留保とは、事業で得た純利益のうち、配当金などを差し引いた後に会社に残った利益のことを指します。
決算書上では「繰越利益剰余金」として表され、黒字が続くほど内部留保は増えていきます。厳密には内部留保と繰越利益剰余金は完全に同義ではありませんが、実務上はほぼ同じ意味で使われます。
内部留保と現金の関係
よく「内部留保が多い=手元資金が豊富」と誤解されますが、実際はそうではありません。
企業が得た利益は、新しい設備投資や人材確保、研究開発費、借入金返済など、将来の成長のために使われることが多く、必ずしも現金として残っているわけではありません。
そのため、「内部留保が多いから賃上げに回すべき」と単純に考えるのは適切ではなく、会計上の概念として理解することが大切です。
決算書での内部留保の確認ポイント
内部留保は、決算書の貸借対照表の自己資本の部に記載されている「繰越利益剰余金」で確認できます。
ここには、会社設立から現在までに積み上げられた利益が反映され、企業の安定性や収益性を評価する重要な指標となります。
内部留保がマイナスの場合の注意点
もし繰越利益剰余金がマイナスになっている場合、それは累積赤字の状態を意味します。
さらに資本金などを含めた自己資本がマイナスであれば、債務超過となり、金融機関からの融資が難しくなる可能性があります。しかし、事業計画や改善策をしっかり示せば、借入が可能なケースもあります。
この点については、資金繰りの改善や補助金活用とも関連があります。詳しくは、資金繰りとは?中小企業が必ず押さえておくべき基本と改善方法をご参照ください。
内部留保の役割と経営への影響
内部留保は、企業がこれまでどれだけ利益を蓄積し、どのように活用してきたかを示す「企業の体力」を表す指標です。
数字だけを見て「ため込みすぎ」と判断するのではなく、資金の使い方や将来への投資方針を理解することが重要です。
内部留保を正しく活用することで、次のような経営上のメリットがあります。
- 設備投資や新規事業への資金源として活用できる
- 借入金返済の安定化に役立つ
- 緊急時の資金不足を補う余裕資金となる
また、内部留保の管理と資金繰りを連動させることで、黒字倒産のリスクを低減できます。内部留保の積み上げと活用計画は、財務の健全性を維持する上で不可欠です。
奈良市で経営・財務に関するご相談は行政書士だいとう事務所へ
奈良市で会社経営をされている方や、財務管理を見直したいとお考えの方に、弊事務所では中小企業向けに幅広いサポートを行っています。
- 法人設立支援
- 補助金・助成金申請サポート(例:ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金)
- 契約書作成・法務サポート
- 決算書作成・内部留保の活用相談
経営の安定化や資金繰り改善のためには、内部留保だけでなく資金計画や補助金の活用も重要です。詳しくは、補助金申請サポートもご覧ください。
「決算書の見方がわからない」「内部留保の増減理由を知りたい」「金融機関への説明資料を整えたい」など、経営に関するお悩みはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料で、貴社の成長と安心をともにサポートいたします。