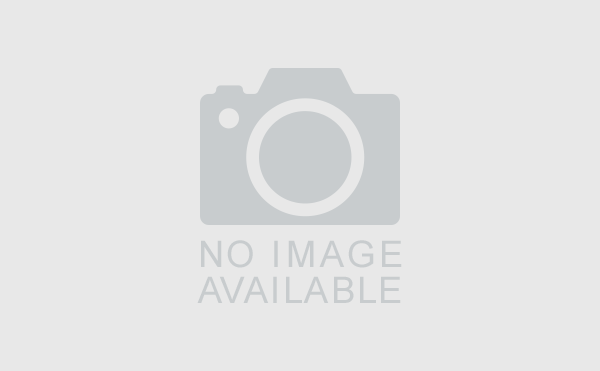お悩み:収益計画ってどう作るべき?融資審査でも有利になる方法は?
中小企業や個人事業主の方から、「収益計画(収支計画)って、本当に必要ですか?」というご相談をよくいただきます。
確かに、日々の業務に追われるなかで、数字の計画を立てるのは後回しになりがちです。
しかし、収益計画を作ることは、会社の“未来を見える化”すること。
単なる数字合わせではなく、経営を安定させ、融資にも強くなるための“羅針盤”なのです。
収益計画とは?収支計画との違い
「収益計画」や「収支計画」という言葉が混同されることがあります。
- 収益計画:売上・利益・コストなど、企業の「稼ぐ力」を中心に見通す計画
- 収支計画:資金の入出金を含めた、資金繰り・キャッシュフロー重視の計画
どちらも重要ですが、経営者が最初に作るべきは「収益計画」。
なぜなら、利益を生む構造を明確にすることが経営の出発点だからです。
収益計画を作る3つの目的
① 経営の見通しを立てるため
過去3~5年の実績を整理し、今後3~5年の売上や利益を予測することで、
「今の事業はどの方向に進んでいるのか」「いつ資金が足りなくなるか」を可視化できます。
② 経営判断の精度を高めるため
計画があると、経費削減・設備投資・新規事業などの意思決定が数字で裏付けできます。
感覚ではなく、根拠ある経営判断が可能になります。
③ 金融機関からの信頼を得るため
銀行や信用金庫は、融資審査の際に「収益計画書」や「資金繰り表」を重視します。
根拠ある計画が提出できれば、融資の通りやすさが格段に上がります。
収益計画の作り方(実践ステップ)
ステップ1:過去実績の分析
まずは過去3~5年分の決算書を分析します。
- 売上・利益の推移(増加?横ばい?減少?)
- 一時的な収入・支出の有無
- 固定費と変動費の構造
- 利益率の変動要因
これを「現状把握」として整理します。
ステップ2:将来の見通しを立てる
次に、今後3~5年の売上・費用・利益を見通します。
- 売上増加の根拠(販路拡大・新商品・客単価向上)
- 経費削減の根拠(仕入れ見直し・無駄経費削除)
- 設備投資・人件費・借入返済の見込み
この段階では「理想」よりも「実現可能性」を重視しましょう。
ステップ3:仮計画を検証する
作った計画が極端になっていないかをチェックします。
- 利益率が急上昇していないか
- 売上目標に実行策が伴っているか
- 経費削減が売上に悪影響を与えていないか
現実的な数値に修正し、計画を完成させます。
作って終わりではない!PDCAサイクルを回す
収益計画は「作ったら終わり」ではありません。
むしろ、実績と比較・分析することが最も大事です。
- 計画より良かった点 → 成功要因を次年度に活かす
- 計画より悪かった点 → 改善点を明確化
このPDCAサイクルを毎年繰り返すことで、計画の精度も経営の安定度も上がります。
金融機関は「収益計画」をこう見ている
金融機関は、融資審査時に以下の視点で計画を評価しています。
| 評価項目 | ポイント |
|---|---|
| 売上計画 | 市場動向や実績に基づく現実的な数値か |
| 利益計画 | 利益構造が持続可能か |
| 資金繰り | 返済能力が十分にあるか |
| 計画書の整合性 | 根拠や裏付け資料があるか |
| 経営者の理解度 | 計画内容を自ら説明できるか |
特に中小企業では、「税理士任せ」「銀行任せ」にせず、経営者自身が数字を理解して説明できることが重要です。
行政書士としてのアドバイス
当事務所は、補助金申請や融資申請支援の場面で、「事業計画」「収益計画」「経営改善計画」などの策定をサポートしています。
数字が苦手な経営者でも、ヒアリングを重ねながら一緒に計画を作り上げることが可能です。
「漠然とした不安を見える化する」──それが、計画づくりの第一歩です。
まとめ:収益計画は“攻め”の経営の第一歩
専門家(行政書士・税理士・中小企業診断士)に相談することでより実践的になります。
収益計画は、経営の方向性を示す“未来の地図”となります。
金融機関の融資審査でも高く評価されます。
作って終わりでなく、定期的に見直すことで精度が上がります。