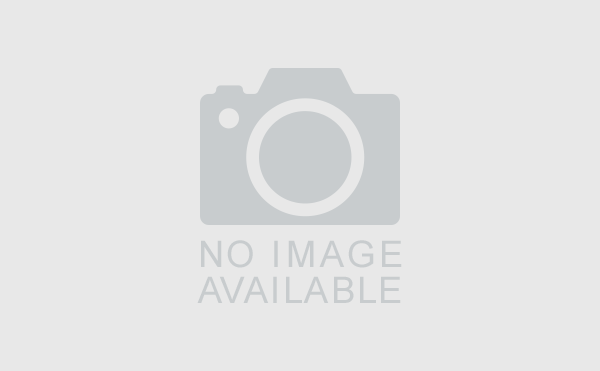お悩み:優越的地位の乱用とは?経営者が知っておくべき法律リスクと防止策
企業が融資を受ける際、金融機関から「融資条件とは別にお願いをされる」ことはありませんか?
たとえば、「定期預金を作ってほしい」「投資信託も契約してほしい」「クレジットカードを発行しておいてください」などといった要請です。
一見すると「ちょっとしたお願い」に思えますが、これが場合によっては『優越的地位の乱用』にあたる可能性があります。
この記事では、優越的地位の乱用の意味・金融取引での具体例・対応策をわかりやすく解説します。
優越的地位の乱用とは?
「優越的地位の乱用」とは、公正取引委員会が定める独占禁止法(第2条第9項第5号)に基づく不公正な取引方法の一つです。
簡単に言えば、立場が強い企業が、取引相手に不当に不利な条件を押し付ける行為を指します。
独占禁止法での定義
取引上優越した地位にある事業者が、その地位を利用して、相手方に不利益な取引条件を受け入れさせる行為。
つまり、相手が断れない立場にあることを利用して、不必要な契約や取引を強要することが問題視されます。
金融機関における優越的地位の乱用
融資取引においては、金融機関(債権者)が圧倒的に優位な立場にあります。
債務者(借入人)は「お金を貸してもらう立場」であるため、金融機関の要請を断りづらいのが現実です。
よくある「優越的地位の乱用」とみなされる行為の例
- 融資条件として投資信託や保険商品の購入を求める
- 定期預金の預け入れを半ば強制する
- クレジットカード契約や給与振込口座の指定を条件にする
- 系列企業の商品・サービス購入を事実上義務付ける
これらの行為は、形式的には「お願い」や「推奨」とされることが多いですが、実態として融資を人質に取ったものであれば、優越的地位の乱用に該当するおそれがあります。
「融資条件」と「お願い」は区別が重要
融資時には、担当者が「この条件でお願いします」と伝えることがあります。
しかし、それが本当に融資実行の前提条件(融資条件)なのか、それとも単なる営業的お願いなのかを見極める必要があります。
| 区分 | 内容 | 優越的地位の乱用に該当する可能性 |
|---|---|---|
| 融資条件 | 担保設定・保証人・返済期間など、融資審査に直結する要素 | 原則なし |
| 営業的お願い | 投資信託契約、定期預金作成、カード発行など | あり得る |
クレジットカードを契約しないと融資が受けられない、というのは冷静に考えれば不自然です。
融資条件と営業行為を混同しないよう注意が必要です。
金融機関側の事情と現実
金融機関としても、店舗や担当者に営業ノルマが存在します。
融資とは別に、投資信託・カード発行・保険販売などの販売実績が評価対象になっているのが実情です。
したがって、「融資を通したいならついでにこちらも…」という圧力がかかるケースは少なくありません。
しかし、金融庁や日本銀行はこうした行為に対して繰り返し「優越的地位の乱用にあたる可能性がある」と注意喚起しています。
近年では、実際に行政指導を受けた金融機関もあります。
強要された場合の対応策
もし金融機関が明らかに不当な「お願い」をしてくる場合、次の対応を検討しましょう。
- 冷静に確認する
→ その条件が本当に「融資条件」なのか、担当者に明確に尋ねる。 - 他行への相談・比較
→ 無理にその銀行だけに依存せず、信用金庫や別の銀行にも打診してみる。 - 記録を残す
→ 強要の経緯や担当者の発言をメモに残す。 - 金融庁・財務局・公正取引委員会への相談
→ あまりに不当な場合、行政機関への報告も可能(ただし最終手段)。
多くの金融機関は、顧客離れや行政処分を恐れるため、無理な「お願い」を続けることはできません。
優越的地位の乱用を避けるために
経営者としては、「借りてあげる」くらいの気持ちで対等に交渉する姿勢も大切です。
また、条件に納得がいかない場合には、その理由を金融機関に確認しましょう。
- 担保余力が不足しているのか
- 財務内容に懸念があるのか
- 返済計画の精度が低いのか
こうした理由を明確にすることで、自社の経営課題が浮き彫りになり、次の融資交渉にも活かせます。
行政書士としての立場から
私が金融機関に勤務していた際は、常に「優越的地位を乱用しないこと」を意識していました。
行政書士となった今も、お客様との関係において「対等な信頼関係」を何より重視しています。
不要な契約やサービスを勧めることは一切ありません。
お客様の立場に寄り添い、本当に必要な融資支援・事業計画の作成支援を行っています。
まとめ
- 優越的地位の乱用とは、立場の強さを利用して相手に不利な条件を押し付ける行為
- 融資時の「お願い」は、実質的な強要であれば違法行為の可能性あり
- 納得できない条件は、必ず理由を確認し、必要に応じて他行比較や行政相談も視野に
- 対等な立場での取引を心がけることで、健全な金融取引が実現できる